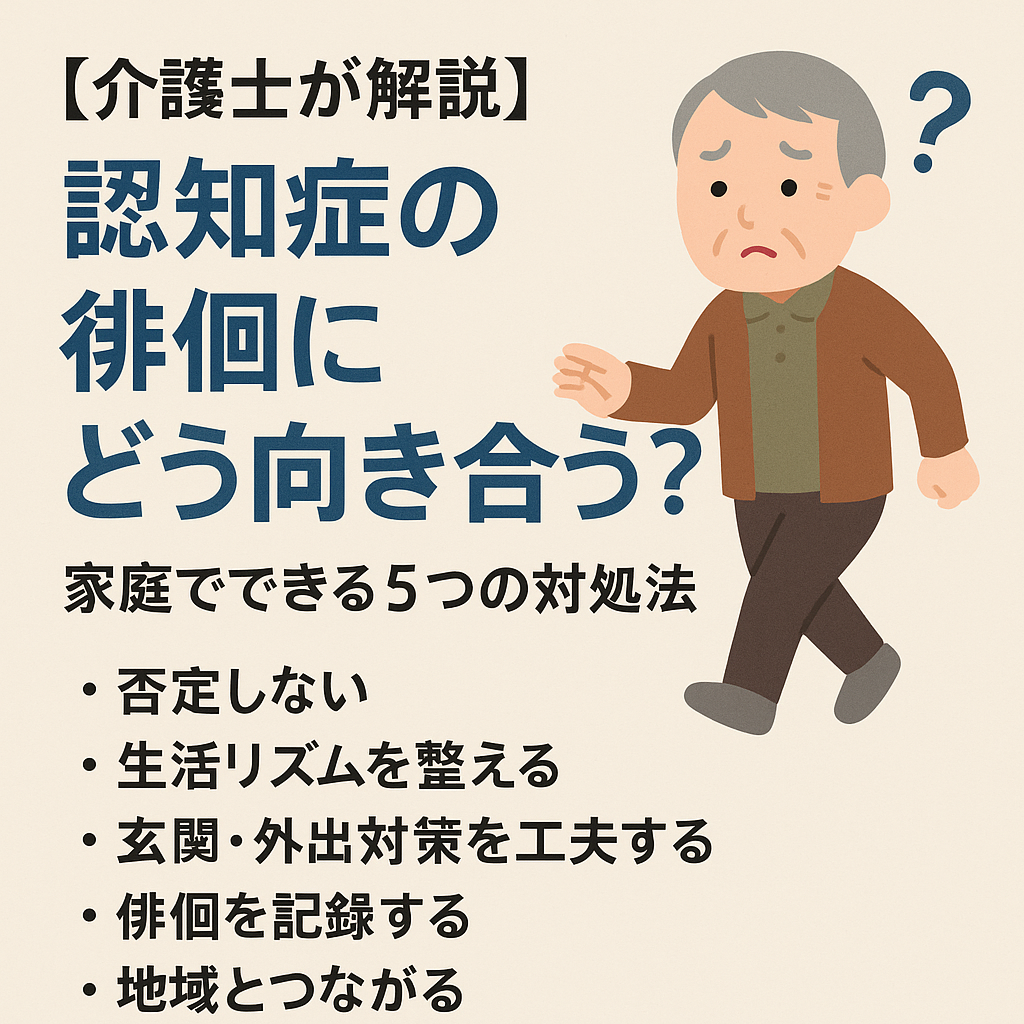高齢者の転倒は“予防できる”|今日からできる高齢者の転倒予防10の実践ポイント

✅ はじめに|転倒は“生活を一変させる”リスクです
「ちょっと転んだだけ」・・・そう思っても、
実際は骨折→入院→寝たきり→認知症と、一気に状態が悪化することも少なくありません。
厚生労働省のデータによると、高齢者の骨折の原因の約7割が「転倒」。
そして転倒は、寝たきりや認知症のリスクを増大させる事が分かっています。
この記事では、介護・福祉の現場で実践されている「転倒予防の10のポイント」を詳しく解説します。
✅ 1. なぜ高齢者は転びやすくなるのか?
年齢を重ねると、転びやすくなる要因が複雑に重なってくるのです。
| 主な要因 | 説明 |
|---|---|
| 筋力の低下 | 特に太もも・足首の筋肉(大腿四頭筋・前脛骨筋) |
| バランス感覚の低下 | 前庭機能や深部感覚の衰え |
| 視力・聴力の低下 | 周囲の変化に気づきにくくなる |
| 認知機能の変化 | 判断力・注意力の低下 |
| 薬の副作用 | 血圧降下剤や睡眠薬などの影響 |
🔍 ポイント
「年のせい」ではなく、具体的な“からだの変化”を知ることが対策の第一歩です。また、認知症になると寿命が短くなるといったイメージがあるかもしれませんが、これは注意力の低下による転倒などの内的な訴因によるものも原因の一つではないかと私は考えています。
✅ 2. 家の中での「転倒リスクゾーン」を特定しよう
✅ 危険な場所ランキング(介護施設でもよくある)
- トイレまでの廊下(夜間照明不足+急ぐ心理)
- 和室の段差・敷居
- お風呂場・脱衣所(すべりやすい+裸足)
- 台所やテーブル周りのカーペット
- 布団の横・ベッド周りの床置き物
✅ 改善チェック:
- 【段差】…スロープや簡易手すりで対策
- 【照明】…人感センサー+足元灯の併用
- 【家具配置】…移動経路をまっすぐに保つ
普段からよく使っている(今までよく使っていた)場所は落とし穴になりやすいです。
✅ 3. 靴・スリッパの見直しで「5歳若返る」
高齢者の転倒原因で多いのが「つっかけ・スリッパによるつまずき」。
👟 安全な室内履きの条件:
- かかとが固定されている(ストラップ付き)
- 靴底に滑り止め加工あり
- 踵と足首に適度なフィット感
- 脱ぎ履きがしやすいマジックテープ式
🧼 さらに:滑り止め靴下やソール交換も併用すると◎
移動しやすい履物に変えるだけで歩行動作が5歳若返ります!
びっくりしませんか?たったそれだけで?って思いますよね(笑)
でも本当なんです。慣れているからと言って見直さない手はありません。
✅ 4. 毎日3分でOK!おすすめの転倒予防運動
🌟 座ってできる簡単運動(柔道整復師推奨)
| 運動 | やり方 | 目的 |
|---|---|---|
| かかと・つま先上げ | 椅子に座って10回ずつ | すね・ふくらはぎ強化 |
| モモ上げ | 片脚ずつ上げて3秒キープ | 股関節・体幹の安定性 |
| 足指グー・パー体操 | 床で指を開閉10回 | 足の接地感を高める |
| ペットボトルつま先タッチ | 前に置いたペットボトルに足をタッチ | 前傾姿勢とバランス訓練 |
📌 ポイント:
食後やテレビの前など、“生活の中に組み込む”のが続けるコツです。
とにかく大事なことは『継続』続ける事です。
習慣として身につくまで続けてみましょう。ほんの数分でも良いんです。気が向いたらいつもより少しだけ長くやってみてください。
絶対に変わります!
✅ 5. 食事と栄養も“転倒予防”の一部です
骨折予防は、筋肉と同時に骨を丈夫にする栄養も大切。
🍽 積極的に摂りたい栄養素:
- たんぱく質:肉・魚・卵・豆製品(筋肉維持)
- カルシウム:牛乳・ヨーグルト・小魚・ひじき(骨)
- ビタミンD:鮭・しらす・キノコ類(カルシウム吸収)
- 水分補給:脱水→ふらつき予防に重要!
食事(栄養)が何より大事になります。丈夫な資本=身体が無ければ運動の質や、そもそもの歩行動作、移動動作時の転倒リスクを増大させてしまいます。
✅ 6. 「ふらつき・めまい」を放置しない
転倒の直前には「ふらっとした」というケースが多くあります。
✅ こんな症状があれば医師に相談:
- 立ち上がった時にクラっとする
- 階段や外出時にバランスを崩す
- 朝起きた時に頭がぐるぐるする
👉 原因:血圧・三半規管・薬の副作用など
転倒してから後悔した…何てことにならないように日頃から気になる事があれば直ぐにかかりつけ医に相談するようにしておきましょう。
安心して相談できるかかりつけ医を見つけておくことも大切です。
✅ 7. デイサービスで“転ばない体”をつくろう
デイサービスは、転倒予防を「習慣化」する絶好の場所です。
| 活動例 | 効果 |
|---|---|
| 集団体操 | バランス力・下肢筋力UP |
| 個別リハビリ | その人に合った運動メニュー |
| レクや歩行練習 | 実際の動作の中で感覚を育てる |
✅ 職員による「生活動作の見守り」も、転倒予防に直結!
運動特化型の施設であれば転倒予防を図りたいと希望を伝える事で希望に沿った訓練メニューを作成してもらえます。
✅ 8. 杖・歩行器は“正しく”使ってこそ効果あり
間違った使い方は逆に危険!
| 正しい杖の高さ | 手首の位置にグリップが来る |
|---|---|
| 歩行器の選び方 | 室内用か屋外用かを見極める |
| 使い始めのコツ | 必ず専門職(PT・OT)の指導を受ける |
最近ではYouTube等のSNSでも気軽に見る事ができますので、ご家族の方も一緒に勉強するのも良いかもしれません!
✅ 9. 薬のチェックを怠らない
高齢者の転倒リスクは、処方薬の影響によることも。
| 薬の種類 | 転倒リスクの影響 |
|---|---|
| 睡眠薬・抗不安薬 | ふらつき・注意力低下 |
| 降圧剤 | 立ちくらみ |
| 利尿剤 | 夜間頻尿 → 寝ぼけて転倒 |
✅ 処方が多い方は、医師や薬剤師に「転倒リスクのある薬か?」と確認を!
服用量を間違えていないか等、定期的にチェックが必要です。
服薬の影響で転倒しました。。。という報告を何度も聞きました。
皆さん必ず公開されていますので、今すぐにご確認を!
✅ 10. 転倒後の“心のケア”も大切です
一度転ぶと、本人が「また転ぶのでは…」という心理的な不安で動かなくなることがあります。
✅ サポートのポイント:
- 転倒を責めない(自尊心を傷つけない)
- 「やれることはある」と励ます
- 専門職と連携し、再発予防のリハビリを支援
💡 転倒を“学びのチャンス”として活かせば、回復も可能です。
メンタルは非常に重要で運動動作に大きく影響を与えます。
プロのトップアスリートですらメンタルが8割なんて言う位ですから、我々もそれ相応の影響を受けている事でしょう。
過去のトラウマから運動を控えがちになったり、動作そのものがリスクの高い動きになってしまうなど大きな影響を与える可能性があります。
転倒後に早期に定期的な運動習慣を持つ事やデイサービスなどの施設を利用し外出の機会を確保する事が非常に重要になります。
✅ まとめ|“転倒は防げるリスク”です
| 対策 | 一言まとめ |
|---|---|
| 環境整備 | 家の中を安全にリセット |
| 運動習慣 | 足と体幹を鍛えて安定感UP |
| 栄養・睡眠 | 身体の土台を整える |
| 医療連携 | 不調・薬の影響を見逃さない |
| 精神的支援 | 自信をなくさないケアが大切 |
💬 最後にひとこと
転倒は、本人の意思とは関係なく起こる“生活事故”でもあります。
だからこそ環境を整え、体を動かし、正しい情報を持つことで、予防することができます。
若いうちであればあるほど後々、効果を実感できる期間が長くなります。
デイサービスでは、こうした転倒予防支援も日々行っています。
「転ぶ前に対策を」は、今日から始められます。
定期的な運動習慣、外出機会の確保を!
この記事が参考になりましたらうれしい限りです。
相談したい事や悩んでいる事がありましたら、お気軽に下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!